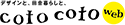見たことの無い洗面台をつくってみよう
世の中の洗面台は丸ごと既製品を使うか、天板に洗面ボウルを埋め込んで作られている。埋め込むだけでも十分オリジナリティーのあるものになり、かつ機能的だが、今回は洗面ボウルまでを自作してみたので、その手順を記す。自分が使うものだから使いにくくても責任が持てるし、問題があっても自分で作れば自分で修正できる。そして何より世の中に見たことの無いデザインはやっぱり作ってみたい性なのだ。
今回作るものはコンクリートの塊のような洗面台。本当に洗面台をコンクリートの形にすることもできるかもしれないが、重すぎたりひび割れの不安があったりするので、木で組んでモルタルで仕上げるコンクリート風のものにする。まずは設計図通りに洗面台の骨組みを組んでいく。たわむと仕上げにする予定のモルタルがひび割れるので、材同士は多めのビスと、ボンドを併用してがっちりと組んだ。組み終わったら一番強度上の弱点である手前の中心に体重を載せてみて、びくともしなければOK。

洗面台が他の家具と違うのは給水管、排水管を通す必要があることだ。逆に言えば給水管、排水管を通す穴さえ開ければ他の家具の作り方と同じなので、なんとなく難しそうなイメージで敬遠し続けるのももったいない。
混合栓取り付け用の直径32mmの穴を開ける。(器具によって違うが、一般に混合栓が35mm、単水栓が25mmで開けることが多い。35mmの穴でよかったのだが、ぎりぎりで入るサイズにしておいた。)位置は水が落ちる位置がシンクの奥から1/3くらいの位置にした。水が落ちる位置も案外重要で、手前すぎると手が入れにくく感じたり顔が洗いにくかったりするし、奥すぎると水が洗面台の上に跳ねやすいので奥から1/4〜1/3くらいが良い。
開けた穴の上から混合栓を通し、下から混合栓の下部についているネジを閉めてテーブルに止めるが、ネジの長さは普通それほど長くないため、分厚い洗面台(おおよそ30〜40mm以上)だと止められない。そこで、事前に水栓設置箇所の洗面台の下を一部掘り込むような造作をしておく。彫り込むサイズは奥まで手が入るサイズでないと水栓取り付け時に苦労する。

排水栓取り付け用には41.3mmほどの穴を開ける。(45mmの穴でも良いが、混合栓の穴と同様、こちらも排水栓のネジがギリギリで入るサイズにしておいた。JIS規格の排水穴径は41mm。)排水位置はシンクの中心にした。

排水栓に接続するSトラップは一般的に日本で使われている32mmの規格のもの。トイレのちょっとした手洗いなどには25mmも使われる。床から出しておいたVP管は床仕上がり面と面一で切り、パッキンをはめこむ。パッキンは色々あるが、50のVP管と32mmのステンレス管に適合するものを間違えずに選ぶ。
水勾配をつくる
排水口に向かって水が流れるように勾配をつくるために、シンクの底に使った30mmの木の板を削った。等高線状にルーターとトリマーで深さを1.5、3、4.5、6、7.5、9mmと変えて掘っていった。各深さの部分を掘るときほんの少しだけ削らずに基準として元の高さの部分を残しておくことで全体を一定の勾配となる深さで彫れるようにした。最後に残ったところを鑿でさらえ、サンダーで等高線を消すように削って仕上げる。
防水層の形成と仕上げ
その後、FRP防水を洗面台の裏以外の全面にかけたが、その手順はTip90: FRP防水のとおり。機能的には防水をかけたら完成でも良いのだが、見た目をコンクリートの塊のようにしたかったので、その上にモルタル風仕上げを施した。
モルタル風仕上げは最近流行っているが、モルタルはクラックや水染みができやすいもので、本来は水がかかる場所の仕上げに向いているものではない。洗面台のモルタルはできれば伸縮性や防水性の高いモールテックスがやはり良いが高い。そこで、全面FRP防水をかけてクラックができても水が漏れることがないようにしてみた。以前、Tip73: 床を組むで組んだトイレの床と同じようにNSカチオンワン#2という樹脂モルタルを下地とし、仕上げに使える高強度薄塗りモルタルのNSハードフロア仕上げとした。
まず、シンク裏側は木下地のままなのでアク止めシーラーを二度塗り。乾いたらカチオンワンを塗りたい面積分に必要な分量をバケツに入れ、水の量をちゃんと量ってかくはん機でしっかりと混ぜていく。こするように全体に2mmほど塗りつけ。洗面台の下は上向きに左官がうまくくっつくか不安だったが土間用の大きいコテにネタをのせてこすればまあまあうまくいった。入隅と出隅も専用のコテを使えばそこそこきれいだ。
ただ、事前に難接着面用に日藻プライマーというものを買っていたのを忘れていた。FRP面には表面に硅砂を振りかけてざらざらに仕上げたので大丈夫だろうが、風呂場では忘れないように塗ろうと思う。
最後NSハイフレックスという下地調整材を5倍希釈で塗って2時間ほど置き、NSフロアハード塗り付け。NSフロアハードは過度な鏝押さえや水打ちをすると白っぽく色ムラになるようだが、素人にそこまで配慮する余裕も無いので鏝ムラは鏝押さえ、水打ちをして丁寧に消し、色ムラはいい感じになることを願いながら仕上げた。
洗面台が仕上がったら壁を塗って、水栓、照明器具等を取り付けて、収納扉と鏡を取り付けたら完成。(このあと、配管を隠す扉を付けて棚を付ける予定。)

丸太を彫り込んで彫刻のように何かを作りたい
このオリジナル洗面台は2作目で、1作目は切ってきた丸太を彫り込んでTip46: スプレーガンで塗装するのようにウレタン塗装で仕上げたので、その手順も記しておこう。
ホームセンターで買ってきた木でなく、切り出してきた大木を使って何かを作りたくて丸太のまま1年ほど放置しておいたナラの木を材料にして作った。乾燥させるために置いていたが、重すぎてダンプで土の上に落とした状態のままだったので虫が湧いているし、全く乾燥していないのは反省。
まず、虫が食っているところを外して木取りの目処を付け、チェーンソーで荒く縦に割る。このとき、中心を外しておくこと。年輪の中心の材を使うと乾燥とともに歪んだり割れたりしてしまう。
電動ミニカンナで水平な表面を作る。横から睨んだり、定規を何度も当てて確認。
各水栓が取り付く位置、材を切る位置を仮で墨付けし、チェーンソーで予定の幅より少し余裕を持って切る。チェーンソーで洗面器になる部分を慎重に彫り込んで荒く形をつくっていく。
木の板の模様や、虫食いなどの様子を見ながら木のどの部分を使うか確定させて最終の墨付けをし、水平面を基準にして指定寸法に切る。
形を修正しながらやすりがけをしていく。
先述の要領で給水栓用の穴を開け、排水栓用の穴を開ける。
洗面台を支えるために左右の壁に止める桟のサイズの彫り込みを洗面台にも作る。
パテで穴埋めし、乾燥後にまたやすりがけ。
完成したら木固め材、目止め剤を塗る。丸太のままだと1年野ざらしで乾燥させた程度では乾燥しきらず変形する。そのためこの作業は何日もかけて行なうと木が割れてくるので、木を割ってから木固め材を塗るまでは手早く行なうのが良さそうだ。
いよういよウレタン塗装だが、その手順はTip46のとおり。
あとは設置して完成。(こちらも配管は後日見えないようにする予定だったがその前に人に譲った。)