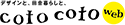戸は開いたり閉じたりするが、当然ぴったり閉じたり開いたりしないといけないため、0.5mm狂うだけでうまくいかなかったりする。まさに建具屋さんの職人技だ。
しかし、素人でも最近の部品に頼る事でそこそこの精度でもちゃんとした建具を作る事ができる。おすすめは吊り戸。最近の部品は良く出来ていて、数ミリであればドライバー1本で戸先側、戸尻側それぞれで戸を前後左右に調整できるようになっている。さらに吊り戸は下に枠がいらず見た目もすっきりするため、今回の家にも多用する計画としている。
部品は一式で以下6点を選んだ。計1万円ほど。
- 上枠に埋め込むレール
- 戸の下に埋め込むレール
- 吊り戸下部ガイド(床に取り付ける戸が前後に振れるのを防止し、まっすぐ動くようにするためのガイド)
- ソフトクローズ吊り車(戸先上部に埋め込むパーツでソフトクローズタイプは戸が閉まる時ゆっくり自動で閉まってくれる)
- ブレーキ付き吊り車(戸尻上部に埋め込むパーツでブレーキ付きのものは開ききる直前にブレーキが作動してくれる)
- ブレーキ作動板
セット品はあまり売っておらず、メーカーのカタログを見ながら選んだが、かなり多くのパーツがあり、そこから自分の目的に適したものを選ぶのはカタログをしっかり読み込まなくてはならず、慣れていないと難しかった。
戸を吊る枠をつくる
まずは吊り戸を吊るための木を加工し、建物躯体に組み込んだ。材料は古材を使い、前の家から丁寧に取り外した敷居の溝をカンナで削ってなくし、歪みを修正した。古材を使うと時間がかかるので面倒だが、表面を削れば新建材と同じように綺麗になる。材料費が節約できるという側面もあるし、よく乾燥しているので狂いにくい。
真っすぐな材になったら建具の吊りレールをはめる溝を切る。レールが20mm幅、21.5mm深さだったので、なるべくちょうどで真っすぐな溝を切った。溝切りという工具も持っていたが、手持ちの刃は幅が7寸=21mmだったため、丸鋸で切った。深さを21.5mmに設定し、何度も真っすぐ走らせて溝を切った。
早速そこそこの精度でなくて大丈夫と言った事と反するが、レールが溝の中に埋まっていなくても吊り戸として機能するので仕上がりの美しさにこだわりが強くなければ建具枠に溝を掘り込まずにそのままレールを取り付けても良いし、枠を固定した後に両側から木材を貼付けて溝加工風にする等すれば難易度はぐんと低くなると思う。
戸をつくろう
戸は枠を組んで表面にベニヤを張って作る、シンプルなフラッシュ戸と呼ばれるものとした。戸の厚みは27mmの枠に両面4mmのベニヤを貼付け、35mmとした。枠はホームセンターで調達した。なるべくねじれやひねりがなく、節のない、しっかり乾燥したものが良いが、高いので安い構造材をまっすぐになるようにカンナがけで調整する事にした。枠の固定は後で取っ手や金具が取り付くところを避けてビスを打って止めた。
表面に貼るベニヤはパテ処理するのであまり関係ないが、試しに部材は45度加工してみた。
木工用ボンドを全面に薄く塗ったらしっかり24時間ほど押さえた。木工用ボンドは学校の授業等で親しみがあり、何となくあまり強くない印象があるが、それは使い方を誤っていたのだった。しっかり押さえて十分に乾燥させることで、例えば2枚の板の断面同士を接着させて1枚の板にできるほどに強度が出る。クランプで押さえたり、プレス機がないので、これでもかというくらいおもりを載せてみたり。
仕上に戸の上の戸尻と戸先には吊り金具をはめる溝加工を、戸の下にはアルミのレールを組み込む溝加工を行う。溝を掘るのはルーターを使う。溝の寸法は金具の説明書に書いてあるとおりに。真っすぐな溝を掘るためにルーターが振れないようにするために、標準で付いていたストレートガイドをもうひとつ購入し、両側にずれないガイドとした。(建具用の治具も販売されていたが、8万円と、家庭用として使うには流石に高かった!)
戸のサイズは高さが1820mm以上あり、ホームセンターにあるベニヤ板などでは継ぎ目ができてしまう。2m x 1mの板材などを材木屋で入手することもできるが、継ぎ目をパテ処理してペンキで仕上げるようにしてホームセンターにある板で済ませることにした。パテ処理とペンキ塗りはTip74: 壁を立てるでやったとおり。
戸の下に振れ止めを設置し、戸のレールにソフトクローズ機能作動金具とブレーキ作動板を設置したら戸を吊って完成。引き手はいい枝を見つけたら取り付ける予定。