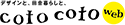Tip41でアルミサッシを使って窓をこしらえたが、窓ってガラスだけ買ってきてはめるだけではいけないのかと思うだろう。もちろんそれで良い。少し施工の難易度は上がるが、サイズや収まりなど、意匠にこだわって作ることができ、手間をかけることができるのなら既製品に頼らないでオリジナリティのある家を作ってみるのはどうだろうか。

今回つくるのはガラスだけ発注して施工する窓のうち最も簡単なガラスをはめるだけ、開かずに殺してしまう、所謂はめ殺し窓を作る。風景を透過して光を取り入れるためだけの窓だ。アルミサッシの家で育ったので玄関に枠のない大きなはめ殺し窓があって庭を臨むのは憧れだった。枠がなければガラスはよりシームレスに内と外を繋げてくれる。
必要なパーツと道具は写真のものとガラスだけ。黒い小さな物体がゴムの板でセッティングブロック、巻いてあるものが硬めのスポンジのようなものでバックアップ材と呼ぶ。残りはコーキング剤とヘラ、ガン、マスキングテープだ。ガラスはインターネットで5mmの強化ガラスを発注した。強化ガラスは普通のフロートガラスより強度があり、割れるときは粉々になって安全だ。価格はフロートガラスの倍程度の値段で、今回は送料込みで2.2万円。横1212mm x 縦1242mmで19kgもありとても重い。ガラスの切断面は触ると切れるほど鋭いので糸面取りをしてもらって少しでも安全に作業ができるようにしておいた。
まずはサッシの時と同じように窓台(窓の下の水平材)とまぐさ(窓の上の水平材)、間柱を入れる。次に、窓ガラスがはまるよう溝をつくる造作をしながら壁や窓台に防水シートを貼る。窓台の外側は削って勾配をつけた木にアルミの水切りをボンドで接着した。もちろん窓まわりは設計で一番大事なところなので図面で入念に検討済みだ。
いよいよガラスをはめる。5mm厚、1200mm余り角の強化ガラスで、19kgほどあるので、慎重に。セッティングブロックはガラスの下に2個、左右の端からガラス幅1/4程度の位置に置いてガラスの自重を点で支える。バックアップ材は窓の内側と外側から窓を挟むように入れていく。溝よりもバックアップ材は大きめなのを無理やり詰め込むので、クッション性によってガラスの端部を内側と外側の両方から抑える力が働く。調べてみるとセッティングブロックと同じように、全周詰め込まなくても良いようなのだが、材料がちょうど全周詰め込む分ぐらいあったので、詰め込んでおいた。ダンボール箱に商品を梱包する時は詰め物のクッションがたくさん入っている方が安定するだろう。このように、ガラスは割れ物を梱包する時のように浮かして木部よりクリアランスを取り、揺れや衝撃で割れてしまわないように施工する。セッティングブロックを入れることでガラスは浮いた状態になり、バックアップ材により溝の内側と外側からガラスをふんわり押さえて動かなくなる。(それぞれ「エッジクリアランス」、「面クリアランス」を確保するためのもので、建築士試験で習ってイメージしにくかったものがようやくイメージできるようになった。)バックアップ材は両側それぞれの溝より少し大きいものを選び、今回ガラス屋さんで一緒に発注したものの直径は6mm。
ガラスが固定されたらあとは隙間を防ぐだけ。この上からマスキングをしてコーキング材を打ち、コーキングべらでならしてマスキングテープを外せば完成。
シリコンコーキングは専用の器具を使ってシリコンを注入していくので難しそうに思うが、新品のマヨネーズをおろす時のようなもので、蓋を開けてフィルムを破って先端をハサミで切ってガンにセットして引き金を引きながらガンを動かしていくだけだ。コーキング材も数百円、ガンも安いものは500円以下で手に入る。覚えておけば、水まわりだとか、雨漏りだとか、水のトラブルへの対応力がアップするだろう。屋外には変性シリコンのもの、屋内にはシリコンのものを使うとより良い。(今回は手元にシリコンのものがあってもったいなかったので屋外にもそれを使用。)
開口部が拓く心地よい世界
ガラスをはめることができれば、内と外を空気的には分断しながら、内に光を取り込み、視覚的に繋がりを得ることができる。分断されていた空間が繋がり、世界に空間を拓く。家と庭がシームレスに繋がることで、家の中にいても外を感じ、家の外にいても中を感じられるような心地よい場所が世界に広がっていく。開口部の作り方で人の導線や行動心理を大きく左右する。開口部こそ建築の要だ。心地よい世界との関わり方を提案できる開口部をつくりたい。
シングルガラスの理由(2025.5.25追記)
なお、今回一枚のガラス板を入れたが、ガラス板2枚で、真ん中に空気層(アルゴンガスが入っていたり真空になっている)をサンドイッチにしたペアガラスというものがあり、現在、住宅を新築するときペアガラスで提案されることがほとんどのようだ。ペアガラスはものによるが普通のガラスよりも倍くらい(商品によっては4倍5倍)熱を通しにくい。家の作りにもよるが、住宅の暖房の熱は半分以上が窓から逃げると言われ、ガラスが熱を通しにくくなると当然冷暖房費の削減になる。それでも今回採用しなかったのはずっと住む訳ではない場所に使うにしてはペアガラスは高価(普通ガラスの3倍以上、商品によってはもっと)というのもあるが、ペアガラスが抱える負の側面を見れば気持ちよく採用できないというのが大きい。
ペアガラスはパッキンが劣化したらガラスでサンドイッチされた空気層に普通の空気が入り込み、内部結露を起こすようになる。結露を起こしても中面は拭くことができず、いつしかカビが生えたり曇ってしまって使えなくなるのだ。カビが生えていなくても断熱性は低下してしまう。一枚板であればほぼ一生使えるはずのガラスがパッキンがダメになるだけでガラスは全交換(サッシは使える)しないといけなくなり、古いペアガラスは廃棄となる。ガラス屋さんは保証などの事情で短めに言っているのかもしれないが、その寿命は10年〜15年と書いているところが多い。
建築が解体されて出たガラスは現在、多くが埋め立て処理されているらしいが、家中のガラスを10年20年ごとに全て交換して知らない土地の地面に埋め立てて放置されるのは気持ちよくないと私は感じてしまう。
今の日本の住宅は平均寿命は約30年と言われ、子供や孫に引き継いで使うことも少ないためそれで十分なのかもしれない。運が良ければ3,40年くらい持つだろうから、次に引き継ぐつもりがなければ家の寿命まで使えるかもしれない。
冷暖房費の側面からエコだとどんな住宅メーカーも標準的にペアガラスやトリプルガラスを採用し、行政からも補助金も出されたりしているが、それはどの家も断熱性と気密性を高めた家で冬はエアコンや石油ストーブ、夏はエアコンを付け続けるという前提での話となっている。夏は自然の風を取り込んで、エアコンを付けずに過ごそうと思うなら夏はガラスの仕様はあまり関係ない。冬は熱が逃げやすいのなら、開口部以外の部分をしっかり断熱し、薪ストーブをガンガン焚いてそれ以上の熱を生み出せば良いと考えている。