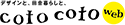4月中旬に差し掛かり、春も本番となってくると行うルーティンがある。特に技術が必要なことではないのだが、時期があり、生活の業でもあると思うので紹介したい。それは、家の周りに粉を撒くことだ。
私と虫をめぐる物語
古民家暮らしはとても憧れると多くの人に言われるが、虫問題は古民家に暮らす人が悩む最も大きな問題だと思う。
私も前の神戸の山の家に住み始めた入居後の初夏、梅雨の前あたりに大量発生するムカデに悩まされていた。ピーク時には一日5、6匹殺すこともあった。仕事をしている机のマウスの横にふと現れたりするので無心で作業ができない。虫は苦手ではないのだが、ムカデは嫌いだ。私自身が噛まれたことはないが、布団の中に入ってきてもぞもぞとした気持ち悪い感触で起こされたり、着た服の中にいて噛まれて痛い思いをしたという話を聞いたことがあり、それを想像するだけでそこが落ち着かない空間となり快適な空間体験を奪われる。
そうは言ってもムカデも家の外に出たすぐそこに生活をしているので、入ってくるなと言うのは難しい問題だ。人間が引いた塀などの境界線などは、自然界には何の意味も無い。
そこで、その境界線をムカデにも教えてやるためにホームセンターでムカデの駆除剤を探してきて家の基礎の立ち上がりのところに1周粉を撒いた。その後数日はたくさん出たのだが、それらを地道に退治してからめっきり見なくなった。おそらく家の中にいた奴らが外に出られなくなってそいつらを全滅させたのだろう。
自分の暮らしをよりよくするためのことを自分で実行するのがDIYの入り口
そういえば、車で2分程のところにある実家ではムカデもゲジゲジも5~10年に1度ほどしか見たことがなかったのだが、父が田植えの準備が始まる4月の中旬頃になると家の周りに粉を撒いていたのを思い出した。父が撒いていた粉にはそう言う意味があったのは知っていたが、撒く時期を考えたのは自分で撒いてはじめてのことだった。
自分で問題に感じて自分で実行して技術だけでなく習慣を身に付けることも、暮らしをよりよくしていく、まさにDIYの入り口だと思う。快適な環境は建物や設備などのハードだけでなく、暮らしのことを自分できちんと行う人間が住んで初めて完成するのだと思う。環境を制御し、住まいをきちんと使いこなせる人でありたい。
私と虫をめぐる物語2 -ムカデの次にやってきた者たち
そうしてムカデ問題が去ってこれで完結したと思いきや、続きの話がある。稲を植え、米の収穫が終わった11月になるとカメムシが大量発生しはじめた。実家も古民家ではあるが、特に対策をしていなくてもあまり見ないのだが、前の家は山の中にあったので生息数がそもそも違うのだろう。彼らは2mmほどの隙間があれば入り込めるらしく、一冬を過ごすあたたかい場所として古民家は最高の環境だろう。冗談抜きで多い日には1日100匹以上部屋の中で殺すこともあった。手荒に退治しようものなら悪臭を放ち、手に付いた臭いは石けんで洗っても取れない。あまり薬剤ばかりに頼りたくないが、手段を選んではいられないので、順番に試してみた。殺しても臭わないカメムシ専用殺虫スプレーはすぐに殺せないし全く臭わせないのも難しかった。カメムシにも対応しているバルサンもほとんど効果がない。

近所の友人に尋ねるとガムテープを背中にそっと貼付け、すばやくくるんで潰さずにゴミ箱に入れてしまうと良いと言うのでやってみると、なるほど確かに臭いがしない。密室に動けないようにされて数日後、ゴミ焼却場で燃やされるという残酷な殺し方だが、あの臭いを出されるとそれぐらいの仕打ちをしたくなる私は僧には向いていないだろう。
これは良いと、その年はガムテープを常に手の届くところに置いておいて乗り切ることとなった。おかげでこれまで実家でカメムシを見た時にはカメムシの動きを見つつ退治するので1匹1分ほどかかっていたのが、服についた引っ付き虫を取るかのように、見つけた瞬間、間髪を入れずに退治する技を身につけた。そうして暮らして季節が過ぎるとともに現れなくなり、さすがに大量殺戮を繰り返したので空き家であった数年のうちに住み着いていたカメムシはいなくなり、もうあまり来なくなったのだろうと安堵した。しかしそれは甘かった。翌年の同じ季節に大量にまた現れはじめた。どうやら杉や檜はカメムシのエサとなるので、単純に私たちはカメムシのご近所に引っ越していたということだった。
翌年もまた近隣住民とともに暮らす生活が始まった。昼には仕事用の机の前の窓に何匹も張り付いているカメムシを何度も退治し、夜には電球の周りをぶんぶん飛び回るカメムシを無視して食事をし、朝一番、つけっぱなしにしている電球の下あたりで死んでいるのを踏まないように足下を気にしながら家の中を歩く生活は、しなくても良い修行を強いられているようだった。さすがにガムテープ作戦をしてこれからも暮らし続けるのを想像すると心が折れた。インターネットに解決策を求めたところ、同じように毎日カメムシを何十匹も退治する人たちからものすごくレビューの高い商品にたどり着いた。
特定の商品をここで出すつもりはなかったが、その効力は唯一無二で「サランラップ」や「ホッチキス」と同じようにもはや一般名詞となってもおかしくない効力なのでその名前を出すと「カメムシ博士」といった。ほかの駆除剤よりも値段が飛び抜けて高かったので足がすくんだが、その異常なほど賞賛する商品レビューを全部読み、藁にもすがる思いで飛びついた。
商品が届いて早速付属のハケでカメムシ博士をアルミサッシの枠、ドアの枠、床下換気口周辺、工事中で壁に穴があいているところなど、侵入できそうな隙間に手当り次第に塗布した。灯油を塗っているような感じであまり塗った感はなく、その塗布当日の夜は飛び回っていたが、翌日いつも窓際にいるよりずいぶん数が少なくなっていた。その夜は飛び回らなくなり、さらに翌日は1匹も見なくなった。
カメムシ博士はムカデやハチなどにも効果があるとのことで、とてもありがたい。カメムシ退治に取られていた時間や奪われていた集中力を考えれば4400円はすぐにペイできるので、同じ悩みを抱える人にオススメだ。
なお、ムカデはホームセンターにある1000円もしないムカデコロリ粉剤がよく効いたのだが、粉なので雨の跳ね返りなどで流れやすかった。そしてしばらく経つと家の中にまた現れた。粒剤を探してみると、カメムシ博士と同じメーカーの出すムカデ博士に結局辿り着いた。6000円もするが、博士なら必ず素晴らしい効果を必ず出してくれると思う私はもう博士ファンだ。ムカデコロリが500gで一度に750gほど、それを年2,3回で3000〜4000円分使っていたが、博士は10kgもあって1年は十分使えるので計算してみるとそこまで価格も悪くはない。それから屋内にムカデは出現しなくなった。
境界線を引くということ
自然の中で快適な空間を作るためには壁で人間同士の境界を作るとともに、自然界との境界をひくことも必要だ。
多くの動物はマーキング等で縄張りというものを示し、それぞれが暮らしている。共存してそれぞれが快適に暮らすために、建築士やデザイナーが引くライン以外の線の引き方を農民たちもまた普段から実践している。
日々の草刈りも野生生物にとっては隠れる場所がなくなるため、そういう境界を引く方法のひとつだろう。伐採や草刈りを行って人間と野生生物の生活圏を分ける「バッファーゾーン」というエリアをつくることで、農産物被害を防止する事業が行政の費用で広く行なわれていたりする。
キャンパーが火を焚いたり、農家が囲炉裏の煙で屋根裏を燻したりするのもそうだろう。
犬やネコと一緒に暮らすことで縄張りを共有して拡張してもらうというのも有効な境界線の引き方のひとつかもしれない。
電気柵やワイヤーメッシュで農地を囲うのも、薬剤をまくのもそのひとつで、手っ取り早いのでどうしても頼りにしてしまう。
今気になっている境界の引き方は、一緒に育てると病害虫が発生しづらくなったり、野菜の成長を促進したり、風味が良くなったりする「コンパニオンプランツ」。自然由来の相性を学ぶことで、生き物同士尊重し合って心地よく暮らすバランスを日々の暮らしの中で探れまいかと思っている。
人間同士の心地よい関係性を築くためのデザインも、実はそういった結界をうまく操作できると作れるかもしれないと思った。