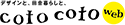工事に無垢の板が欲しかったので、丸太から板を挽いてみることにした。山に生えている木はスライスすれば無垢の立派な板だ。いいものは製材されて何十万何百万の値がつく。素材は半年ほど前に伐採で持ち帰って野ざらしにしておいたヒノキの丸太。手動の鋸ではかなりの時間がかかるし、製材所にあるような大きな機械は買えないので、今回はチェーンソーを使う。木を伐採する時には木を横に切って丸太にするが、今回は縦に切っていく。これを縦引きと呼んでいて、大工ののこぎりも縦と横と違う鋸を使ったりする。
本当はもっと木を乾燥させるために寝かせておいた方が良いし、チェーンソーもより排気量のあるものと縦引き専用の刃が良かったり、まっすぐな板を挽くために治具が必要だったりするようだが、板がないと工事が進まないので、とりあえず手元にあるチェーンソーを使ってフリーハンドで切り出してみた。欲しいチェーンソーや治具も高額だし失敗したら薪にしてしまって他にもある丸太でまたやれば良い。

まずは木におおよそ真っすぐなラインを引き、丸太を地面から浮かして上から切って行く。チェーンソーはなるべく根元を使って切った方が良いのだが、今回はまっすぐな板にしたかったので、大工でまっすぐ鋸を引くときのようにチェーンソーを寝かし気味にして丸太に引いたラインを先に削りつつ、刃を真上から見てなるべく力を抜いて、チェーンをあまり押し付けずに回転する力に任せて切る。1.3mほどを切るのに給油を2回、30分ほどかけてワンカット。若干曲がってしまったところはカンナがけしたら、なんとか様になった。
それからさらに30分かけてもうワンカットして平らな1枚板にして無事に台が完成。60分間チェーンソーの刃をフル回転させて同じ姿勢で切るというのはなかなかの重労働で、もう一枚切り出す気力は失せてしまったので、のこりの半分の丸太は丸太を彫り込んだものに載せて、後日簡易ベンチに。昔は製材所にある大型の機械はおろか、チェーンソーすらなかったため、当然手作業で、割ったり大鋸という巨大なのこぎりで切っていたのだから途方もない作業だ。
製材前の乾燥が甘いと木がさらに乾いてひび割れたりねじれたりひねったりと暴れてくるが、経過観察としよう。簡易計測器での現在の含水率は11〜24%。
ホームセンターに並んでいる板は山に生えている木。
丸太から一枚の板を挽いてみただけだが、それを家のリフォームに使ってようやく山は大事な資源であることを実感することができたような気がする。もちろんそれは言葉では分かっていた。ただ、柱や梁になった部材だけを見ていたので、建築を学んでいながらそういう意識はなかったように思う。スーパーに並ぶ肉はどういうふうに肉になっているかを知っているけど実感している人は少ないのと似ているかもしれない。そこらに生えている木が板になったり柱になって家に使われるのかと考えてみると、使いやすいから棒状の四角い柱や真っすぐな板になっているが、例えば丸いまま、あるいは曲がりを生かしたデザインもあるだろうな、と思った。ヒノキや杉、松が家の材料によく使われているのは加工しやすいのもあるが、幹が真っすぐ伸びるからだということもよく分かった。流通に乗らなくても材料が手に入るから発想が広がる。次は曲がったものや凹凸のあるものをうまく使ってみたい。